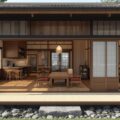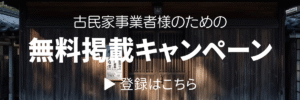補助金ありきで事業を始めると失敗する?計画倒れを防ぐ3つの視点
◆ はじめに:補助金を「目的」にしていませんか?
「せっかく補助金に採択されたのに、半年後にはお店を閉めてしまった。」地方で古民家活用に関わっていると、そんな話を何度も耳にします。共通しているのは、補助金を“目的”にしてしまったこと。申請が通る=やる価値がある、と勘違いし、肝心の“継続力”を置き去りにしてしまうのです。
一方で、同じく採択されたのに今も続く事業者もいます。その差は資金力やセンスではなく、「補助金との距離感」でした。この記事では、補助金に“依存しない”ための3つの視点を紹介します。
1.「補助金があるからやる」ではなく、「やりたいことを通すために使う」
補助金はあくまで手段。制度の存在を知った瞬間に「この補助金に合う事業をつくろう」と逆算しがちですが、まずは「なぜ古民家でやるのか」「誰に価値を届けたいのか」を先に決めるのが筋です。
長浜市で雑貨+喫茶の複合店を開いたオーナーは、申請準備で対象外の設備が多いと気づき、補助金に合わせて店を作る発想をやめました。代わりに理想の空間から逆算して、使える部分だけ補助金を当てる設計へ。助成額は半減したものの、開業後の満足度と来店体験の質は上がりました。
制度に事業を合わせると、採択後に「やりたいこと」と「できること」のギャップが発生しがち。
2.「もらえる」より「続けられる」かで判断する
多くの補助金には継続義務(3〜5年)や成果報告が伴います。古民家は固定資産税・メンテナンス費も毎年かかるため、維持コスト込みの損益ラインを把握しておくことが重要です。
あるカフェは補助金で高級家具に投資し、半年で資金ショート。別の店舗は補助金を厨房設備中心に配分し、内装はDIYで抑制。運転資金に余白を残した結果、安定運営に成功しました。
「家具よりも“続けるための余白”」という発想転換が、後の資金繰りを救います。
3.「採択されるか」ではなく「採択後、どう使うか」を設計する
申請が通ることをゴールにすると、受給後の設計が甘くなりがち。改修費で使い切ってしまい、広告・Web・写真・発信の予算が残らず集客でつまずく例は多いです。
京都の工房兼ショップでは、補助金の2割をプロモーション費に充当。開業前からSNS・写真・LPを整備し、3ヶ月で黒字転換しました。補助金を“未来の集客資金”として活かした好例です。
事例:あえて「使い切らなかった」古民家カフェの判断
岐阜県のカフェAは採択200万円のうち150万円のみを使用。残りは運転資金へ回し、オープン後の仕入・人件費・広告に充当しました。「もらった分は全部使う」を捨てたことで、初期の資金繰りに余裕が生まれ、軌道に乗せやすくなりました。
「全部使わない勇気」が、継続できる経営を支えることもある。
◆ まとめ:補助金は“きっかけ”、主役は事業計画
- やりたいこと→手段の順に決める(制度に合わせて事業を作らない)
- 「もらう」より「続ける」を重視(維持コストと運転資金)
- 採択後の配分設計(改修だけでなく集客・発信にも投資)
この3つの視点があれば、補助金は“リスク”ではなく“推進力”に変わります。
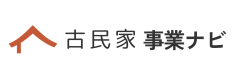
や、改修.jpg)