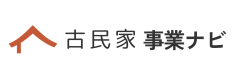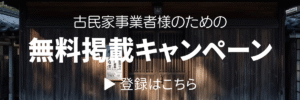古民家を民泊に活用するための法律と許可のポイント
◆ はじめに:夢の古民家民泊、その前に立ちはだかる“法律の壁”
「古民家をリノベして民泊にしたい」――そう考える人は増えています。旅行者にとっては“非日常体験”、オーナーにとっては新しい収益源になるからです。
でも、その夢を現実にするには 必ず「法律と許可」の壁をクリア する必要があります。無許可営業は罰則や近隣トラブルに発展する恐れも。
この記事では、古民家を民泊にするために最低限知っておきたい法律と許可の流れを整理しました。

古民家再生の費用と採算ライン【回収シミュレーション】
◆ はじめに:最初に気になるのは「いくらかかるのか?」
古民家を事業に活用しようと思ったとき、最初に立ちはだかるのが「お金の壁」です。「古民家...
民泊に関わる主な法律
- 旅館業法:ホテル・旅館・簡易宿所などとして営業する場合に必要。古民家民泊は「簡易宿所営業」に分類されることが多い。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法):年間180日以内の営業なら 届け出 で可能。副業や小規模運営に向く。
- 建築基準法・消防法:避難経路、耐震、火災報知器・誘導灯など。古民家では消防対応がハードルになるケースが多い。
これらに適合して初めて「民泊」として認められます。
許可・届出の流れ
旅館業法(簡易宿所営業)の場合
- 保健所へ事前相談
- 図面や改修計画を提出
- 消防署で設備確認(火災報知器・誘導灯など)
- 保健所による立入検査
- 許可証交付 → 営業開始
改修工事の前に相談するのが鉄則です。後戻りコストを防げます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の場合
- 都道府県や市町村に届け出(オンライン対応の自治体もあり)
- 住居としての要件確認
- 年間営業日数180日以内の管理体制を整備
- 届出番号取得 → 営業開始
どちらを選ぶかで必要書類・費用・営業日数制限が変わります。
ケーススタディ:Bさんの失敗例
古民家を改修して民泊を始めようとしたBさん。補助金も獲得し改修も完了。しかし消防署への相談を後回しにした結果、消防設備基準を満たせず営業開始が半年遅延。追加工事に100万円以上かかり、資金繰りが厳しくなりました。
許可申請は「工事前の相談」が鉄則。まずは保健所と消防署へ。
民泊に向く古民家とそうでない古民家
- 向いている:観光地に近い/避難経路が確保しやすい/水回りの改修が容易
- 向いていない:耐震性が低い/消防設備の設置が難しい/立地が不便すぎる
物件選びの段階から「法律クリアのしやすさ」をチェックしましょう。
採算性と法律の関係
- 消防・建築基準対応で追加100万〜300万かかるケースも
- 許可が取れればAirbnbなどOTAに登録可能 → 安定集客につながる
- 清掃・予約管理は代行サービス活用で法令遵守体制を整えやすい

古民家活用で使える補助金・助成金まとめ【2025年最新版】
◆ はじめに:補助金は古民家ビジネスの強い味方
古民家を事業にしようと思っても、改修費や設備費は数百万単位。「お金がネックで動けない」と...
◆ まとめ:まずは相談から始めよう
古民家民泊の実現に必要なのは「資金」や「物件探し」だけではありません。法律と許可をクリアして初めて、安心して事業を続けられます。
- 旅館業法か住宅宿泊事業法かを選ぶ
- 消防法・建築基準法の要件を満たす
- 保健所・消防署への早めの相談が成功への第一歩